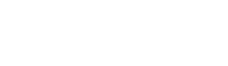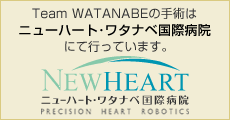心臓血管外科医渡邊剛の40年の軌跡 ~My Story~
オフポンプCABGを行う上で必要なデバイス
「スタビライザー」開発のストーリー
オフポンプCABGにおける最大の課題は、動いている心臓の表面を走る直径1.5mmの血管に、体の他の部位から採取した同じく1.5mm程度の血管を正確に縫ってつなぐ点です。心臓が止まっていれば吻合を行うことは容易ですが、オフポンプCABGでは難しくなります。
オフポンプの場合心臓は動いており、その表面を走る細い冠動脈も常に動いているうえに、血管そのものは心臓の筋肉に血液を流しています。その血管に新しい血管をつなぐためには、短時間であっても血流を遮断する必要があります。血液を遮断している間に血管を切り開き、そこに1.5mmの細い血管を髪の毛ほどの細さの糸で迅速に縫い付ける必要があります。また、血流を止めている時間は“虚血”といい、血液が流れていない状態ですから、長時間続くと心筋梗塞を引き起こしてしまうリスクもあるのです。
この手術に必要な物は3つ、①性能の良いスタビライザー、②迅速かつ正確に血管を縫合する技術、③冠動脈遮断時間中の血流を維持できる方法を考案することです。
それぞれの技術の詳細は割愛しますが、当時は世の中にそのような機械は存在しませんでした。そこで、私たちは自ら考案し作り上げました。スタビライザーについては、かつて身近な生活用品を使って試作を行った時代がありました。食事の際に使うフォークの中央の脚を切り取り、冠動脈をまたいで圧迫し、心臓の動きを止められるようにしたのが実験的に作った最初のスタビライザー第1号でした。その後ドーナツ型の吸盤を開発し、心臓表面の非動化が飛躍的に向上しました。さらにその吸盤を開胸器に蛇腹で固定する発明をしました。アメリカの学会で報告した後、私たちのアイディアを模倣してアメリカの企業がオフポンプ用デバイスを世界に販売するようになったのです。